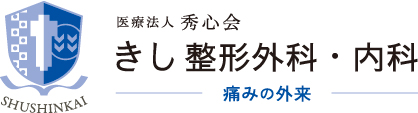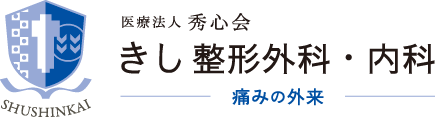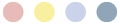
慢性疲労症候群
慢性疲労症候群とは?
通常、私たちが日常生活の中で感じる一般的な「疲れ」などは、安静や休養、睡眠などで回復するものですが、慢性疲労症候群の場合はいくら休んでも回復しない、原因不明の病的な全身疲労感が出現してきます。 その上、全身疲労感以外に風邪症状にも似た微熱、喉の痛み、リンパの腫れ、頭痛等、また他にも数多くの不定愁訴を伴うことがあります。 これだけ様々な症状が現れているにも関わらず、検査では異常が発見できないため、慢性疲労症候群の診断をつけることは非常に困難です。 また診断できたとしても慢性疲労症候群の原因は特定出来ておらず、特効薬も確定される治療法もまだ見つかっていないのが現状です。 また、慢性疲労症候群の患者様は社会生活に支障をきたしてしまいます。やる気はあるのに体がだるくて、外出や軽作業すら出来ない場合もあります。 それどころか、症状の度合いによっては食事など日常当たり前の日常生活ですら困難な状態で、人に色々と助けてもらわなければ、成り立たない場合もあります。 また周囲から見ると元気そうに見えるので、病気ではなくただの「怠け病」と思われてしまうこともこの病気の患者様を苦しめます。 自分の辛さを理解されない苦しみも同時に感じてしまうことは病態を悪化させてしまう原因にもなりうると考えられます。
原因
1. |
感染症 (インフルエンザウイルス、サイトメガロウイルス、エンテロウイルス、EBウイルス、ボルナ病ウイルス、肺炎クラミジア、リケッチア、マイコプラズマなど) |
2.︎ |
ストレス |
3. ︎ |
外傷 |
4.︎ |
代謝異常 |
5. ︎ |
その他 (化学物質、紫外線、アレルギー、外科手術、出産、遺伝、環境など) |
症状
1. |
疲労感 |
2. |
痛み |
3. |
過敏性 |
4. |
睡眠障害 |
5. |
精神障害 |
6. |
中枢神経障害 |
7. |
全身症状 |
診断 (厚生省慢性疲労症候群 (CFS) 診断基準)
A.大クライテリア(大基準)
生活が著しく損なわれるような強い疲労を主症状とし、少なくとも6ヵ月以上の期間持続ないし再発を繰り返す(50%以上の期間認められること)。 病歴、身体所見、検査所見で別表*に挙けられている疾患を除外する。
B.小クライテリア(小基準)
ア) 症状クライテリア(症状基準)※以下の症状が6カ月以上にわたり持続または繰り返し生ずること
1. |
徴熱(腋窩温37.2~38.3℃)ないし悪寒 |
2. |
咽頭痛 |
3. |
頚部あるいは腋窩リンパ節の腫張 |
4. |
原因不明の筋力低下 |
5. |
筋肉痛ないし不快感 |
6. |
軽い労作後に24時間以上続く全身倦怠感 |
7. |
頭痛 |
8. |
腫脹や発赤を伴わない移動性関節痛 |
9. |
精神神経症状(いずれか1つ以上) |
10. |
睡眠障害(過眠、不眠) |
11. |
発症時、主たる症状が数時間から数日の間に出現 |
イ) 身体所見クライテリア(身体所見基準)※少なくとも1カ月以上の間隔をおいて2回以上医師が確認
1. |
微熱 |
2. |
非浸出性咽頭炎 |
3. |
リンパ節の腫大(頚部、腋窩リンパ節 |
⚫︎ |
大基準2項目に加えて、 |
|
小基準の「症状基準8項目」以上か、「症状基準6項目+身体基準2項目」以上を満たすと「CSF」と診断する。 |
⚫︎ |
大基準2項目に該当するが、 |
|
小基準で診断基準を満たさない例は「CSFの疑いあり」とする。 |
⚫︎ |
上記基準で診断されたCSF(「疑いあり」は除く)のうち、 |
|
感染症が確診された後、それに続発して症状が発現した例は「感染後CSF」と呼ぶ。 |
慢性疲労の程度の表し方
PS (performance status)によって疲労の程度を数値化します。
1. |
倦怠感がなく平常の生活ができ、制限を受けることなく行動できる。 |
2. |
通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、倦怠感を感ずるときがしばしばある。 |
3. |
通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、全身倦怠の為、しばしば休息が必要である。 |
4. |
全身倦怠の為、月に数日は社会生活や労働ができず、自宅にて休息が必要である。 |
5. |
全身倦怠の為、週に数日は社会生活や労働ができず、自宅にて休息が必要である。 |
6. |
通常の社会生活や労働は困難である。軽作業は可能であるが、週のうち数日は自宅にて休息が必要である。 |
7. |
調子のよい日は軽作業は可能であるが、週のうち50%以上は自宅にて休息している。 |
8. |
身の回りのことはでき、介助も不要ではあるが、通常の社会生活や軽作業は不可能である。 |
9. |
身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50%以上は就床している。 |
10. |
身の回りのことはできず、常に介助がいり、終日就床を必要としている。 |
治療方法
慢性疲労症候群の治療法はいまだ確立されていません。 内科的な治療として、補中益気湯という漢方薬やビタミンB12、ビタミンCなどを投与されるケースが多いようです。 症状によっては、痛みには鎮痛剤を、うつ状態には抗うつ剤、睡眠障害には睡眠薬を投与するケースもあります。 また、肉体的・精神的な安静状態も大きなポイントとなります。 当院では慢性疲労症候群の患者さまにマイヤーズカクテル点滴をお勧めしております。 実際治療をした方は若干名ですが全員効果がありました。
よくある質問
- 小児でも慢性疲労症候群は発症しますか?
- 日常的に疲れを訴える子どもが増えており、睡眠不足やストレスが背景にあり、不登校や引きこもりの子どもの多くは慢性疲労症候群と考えられています。実際に小児の慢性疲労症候群の診断基準はあります。
小児慢性疲労症候群の診断基準(厚労省研究班)
原因不明で30日以上続く慢性疲労。休んでも改善せず活動レベルが低下
以下のうち主症状2項目を含む4項目以上が該当
〈主症状〉
① 記憶力・集中力の低下 ② 睡眠異常 ③ 疲れやすく、休んでも回復しない ④ 頭痛・頭が重い
〈副症状〉
① のどの痛み ② 首やわきの下のリンパ節痛 ③ 筋骨格系の痛み ④ 腹痛・吐き気 ⑤ 微熱 ⑥ めまい
睡眠の慢性的欠乏による体内時計の狂いが原因と考えられ、早寝早起きリズムの回復が必要です。 小学生の0.5%、中学生の3%が慢性疲労症候群であると考えられています。 不登校を『怠け癖』とか『こころの問題』と決めつけるのでなく、慢性疲労症候群も念頭におかなくてはなりません。 治療は早寝早起きをすること必要があればメラトニンを処方して睡眠のリズムを戻すことが大切です。