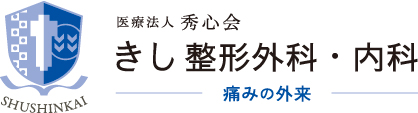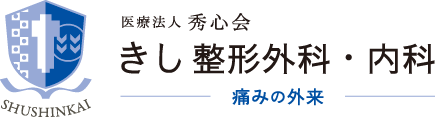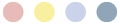
診療項目
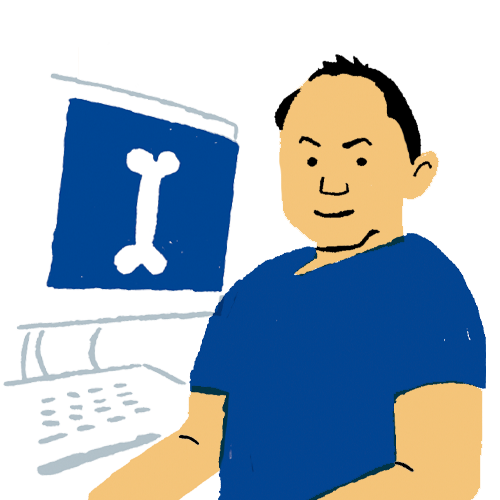
整形外科
Orthopedic surgery
詳しくはこちら
☐︎︎ 腰痛、頚部痛、膝の痛み、肩こり
☐︎ しびれなどの知覚障害
☐︎ 手足の変形、腫れ、運動障害、姿勢異常、歩行障害
☐︎ リウマチ、痛風などの関節疾患
☐︎ 骨粗鬆症
☐︎ 骨折・脱臼・捻挫・打撲などの外傷
☐︎ スポーツ障害・スポーツ外傷
☐︎ 擦り傷・切り傷
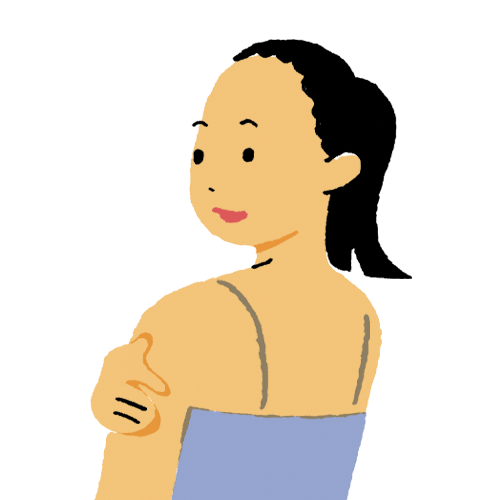
形成外科
Plastic surgery
詳しくはこちら
☐ 陥入爪(巻き爪)
☐ アテローム(粉瘤)
☐ 傷跡(瘢痕:はんこん)
☐ 外傷、熱傷、ガングリオン、バネ指、脂肪種、異物除去(トゲ・ガラス等)、ホクロ、皮膚潰瘍、鼻骨骨折
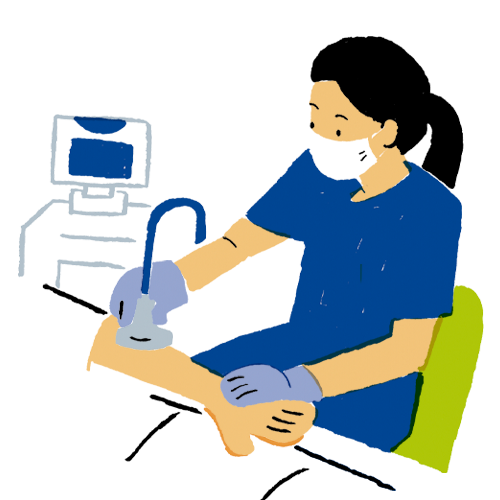
ペインクリニック
Pain clinic
詳しくはこちら
☐︎ 星状神経節ブロック
☐︎ 三叉神経ブロック
☐︎ 腕神経叢ブロック
☐︎ 椎間関節ブロック
☐︎ トリガーポイントブロック
☐︎ 硬膜外ブロック
☐︎ 後頭神経ブロック
☐︎ 肋間神経ブロック
☐︎ 腰部交感神経ブロック
☐︎ 神経根ブロック
☐︎ 肩甲上神経ブロック
☐︎ 大腰筋筋溝ブロック
☐︎ 不対神経節ブロック
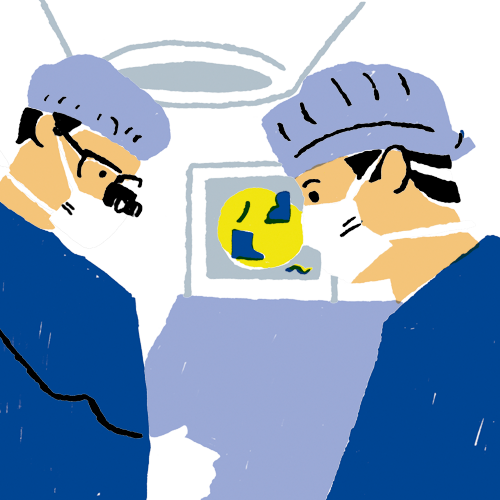
最新医療トピック
latest Medical care
詳しくはこちら
☐︎ 脳脊髄液減少症
☐︎ 巻き爪矯正技術 VHO
☐︎ マイヤーズカクテル点滴
☐︎ 線維筋痛症
☐︎ 慢性疲労症候群
☐︎ イオントフォレーシス
☐︎ 帯状疱疹ワクチン
☐︎ がん治療
☐︎ ANK リンパ球療法
健康診断
当院では、健康診断も受け付けております。(予約制) 身長・体重・腹囲 胸部レントゲン・心電図 視力・聴力・色覚 血液検査・尿検査・etc.. (血液検査は食後12時間以上経過した状態で行いますのでご注意ください) 上記記載等の一般的な検査は当院にて検査可能です。 また、法人様向けの団体健診も承っております。 日時や検査項目、料金等のお問い合わせは事前にお電話にてご確認ください。 ※当日の混雑を避ける為、事前にご予約をお願いいたします。
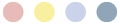
産業医について
産業医とは、事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師を云います。 産業医学の実践者として産業保健の理念や労働衛生に関する専門的知識に精通し労働者の健康障害を予防するのみならず、心身の健康を保持増進することを目指した活動を遂行する任務があります。 産業医が必要なご企業様、産業医についてお困り・ご相談の有るご企業様は、事務長の森作まで御連絡下さい。
産業医の選任
常時50人以上の労働者が働く事業場では産業医を選任することが義務付けられています(労働安全衛生法)。 なお常時1.000人以上の労働者が働く事業場または有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、専属の産業医を選任しなくてはなりません。 また、常時3,000人以上の労働者が働く事業場では2名以上の専属の産業医を選任しなければなりません。 専属産業医を選任しなくてもよい事業場(50人以上999人以下)では嘱託産業医を1名選任することになります。 一般的には事業場の近くの開業医に委嘱されることが多く、事業者との委嘱に関する契約は、所属の医師会をとおし正式文書を取り交わして行われるようになってきています。 委嘱契約が成立すれば、事業者は所管する労働基準監督署長に産業医選任の報告書を提出することになります。 このことは産業医活動・地域医療・かかりつけ医推進にかかわる大切な仕事と考えています。
産業医の職務
産業医の職務の内容は健康障害の予防と労働者の心身の健康保持、増進に資することを目的とした広い範囲にわたるものです。 産業構造の変革、労働者の高齢化、IT技術の進展にともなう作業態様の変化、メンタルヘルス・過重労働問題等社会情勢の変遷に対応して業務の重点項目も変動します。 また、健康情報管理の問題や事業者の健康配慮義務は新しい法律の施行や裁判所の判例によって対策の在り方が変わってきます。
職場巡視
産業医は事業場(事業者)と労働者の間にあり、労働者の健康を保持・増進して労働と健康を図らなければなりません。 そのために産業医は事業場と労働内容を熟知する必要があります。 職場巡視は毎月行われ、作業方法や作業環境が人体に有害の恐れのあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止する処置を講ずる必要があります。 また衛生委員会・安全委員会などの構成員として会議に出席して意見を述べることが出来ます。
産業医の使命
労働衛生管理体制のなかで、産業医の使命は重要です。医師として中立の立場から発言し、行動しなければなりません。 そして職場巡視などを通じて労働者の健康の保持・増進を図り、健康と労働の両立を樹立させるという尊い使命を有していると考えます。