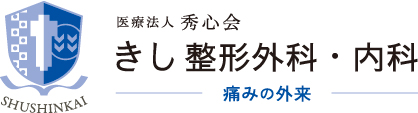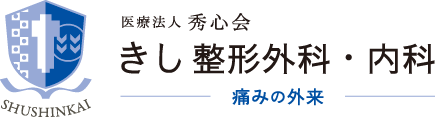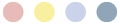
予防運動・自宅療法
予防体操や各症状の自宅療法を詳しくご紹介しています。
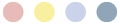
肩こりについて
肩こりは、不良姿勢や骨や椎間板の変性のほか、高血圧、目の異常、ストレス、睡眠不足、更年期障害などからくるものもあります。 病気からくる肩こりではその原因疾患の治療が大切ですが、病気が原因でない肩こりの場合、体操や日常生活での注意により予防したり改善を図ることが大切です。
日常生活で注意すること
- 肩こり体操、ウォーキングなどで体を動かす習慣をつける
- 首や肩に負担をかけない姿勢を心掛ける
- 長時間同じ姿勢をしない
- 首、肩、足の冷えに注意する
- 自分にあった枕を選ぶ
ウォーキングにより下肢の筋肉ポンプが働き、首肩の血行も改善されます。
首が前傾した(あごが前に出ている)姿勢は首、肩に負担をかけます。
「仕事中でも時報を聞いたら、必ず一旦手を止めてストレッチをする」などの工夫を。
血行改善が一番の肩こり予防です。 夏のクーラー対策や、冬は入浴後に髪を濡らしたままにしない、などの工夫を。
頚椎が正しいカーブを保てるような枕を選びましょう。 枕は頭を支えるのではなく、首を支えるのが正しい使い方です。
肩こりの予防体操
筋肉を静かにじわっと伸ばし、その姿勢を20~30秒保持します。 呼吸は自然に。筋肉に軽く張りを感じる程度に心地よく行います。 イスに座ったままでできる簡単な体操ですが、可能なら立ち上がって行ってください。
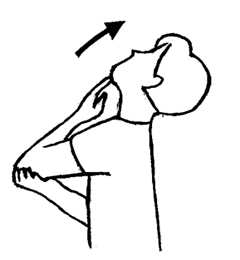
首の前の筋肉を伸ばす
指であごを押し上げます。もう一方の手で肘を支えるとよいでしょう。
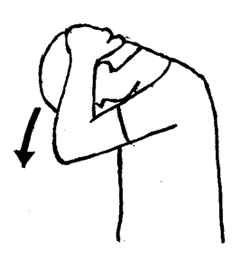
首の後ろの筋肉を伸ばす
両手で首を下に曲げるようにします。
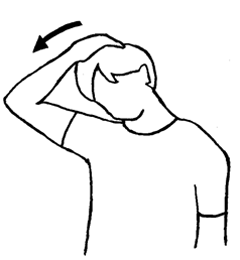
首の横の筋肉を伸ばす
首を右に倒し、左側を伸ばします。
左手でイスをつかみ、左肩が上がらないように押さえるとより効果的です。
反対側も同じように行います。
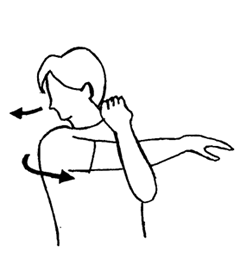
腕の外側と背中の筋肉を伸ばす
右腕を伸ばした状態で、右肘に左腕を引っ掛けて右腕全体を体に近づけます。
この時、顔は右を向きます。
反対側も同じように行います。

脇の筋肉を伸ばす
右肘を左手でつかみ、下へ引っ張ります。
この時、右手で右の肩甲骨を触るようにします。
反対側も同じように行います。
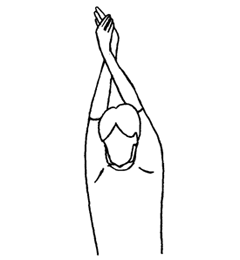
腕の後ろの筋肉を伸ばす
頭の上で手を組み、両肘を伸ばしたまま後ろへ倒します。
同時に、胸を張るようにします。

胸の筋肉を伸ばす
両手を後ろで組み、上へ持ち上げます。
この時、しっかり胸を張るようにします。
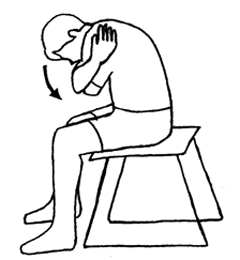
背中の筋肉を伸ばす
胸の前で両腕を組み、それぞれ反対側の肩をしっかりつかみます。
この状態で上半身を前に倒します。
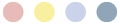
肩関節周囲炎について
肩関節周囲炎(いわゆる「四十肩」、「五十肩」)は中年以降に発生することが多く、老化による組織(筋肉、靭帯、関節包など)の変性を基盤として、肩の痛みと運動制限を現す疾患です。 肩関節周囲炎は長期にわたって痛みが続くことが多く、痛みのために関節を動かさないことで、肩関節の拘縮や肩周辺の筋肉の萎縮を引き起こし、痛みがなくなった後にも残ることがあります。 こうした可動域の制限を残さないために、早期に運動療法を始めることが大切です。
日常生活で注意すること
- 肩を冷やさないよう、保温を心がける(ただし、急性期は冷やします)
- 夜間の痛みがある場合は、寝る姿勢に気をつける
冬にはホッカイロを貼るのも良い(低温ヤケドに注意) 就寝時には布団から肩が出ないような工夫を
痛い肩を上にして横向きに寝る場合は、クッションを抱きかかえる あおむけに寝る場合は、痛い肩の下に丸めたタオルを入れて肩を浮かせる
運動療法
肩関節周囲炎には、炎症と痛みの強い急性期と、拘縮が現れる慢性期があります。 急性期に無理な運動をすると炎症を悪化させることがありますので、この時期には安静を保つことが大切です。このため、電気治療や注射によりできるだけ早めに急性期の炎症を抑え、早期に運動療法を始められるようにしましょう。 なお、運動療法を始めるときには、必ず医師によく相談してから行うようにしてください。
<アイロン体操>
①痛くない方の手を台にのせて上半身を前に倒し、痛い方の手でアイロン程度の重さ(約1kg)のおもりを持ちます。
②肩の力を抜き、からだ全体を揺らすことにより、おもりの重さを利用してゆっくり振ります。
初めは小さく、次第に大きく動かしていきます。ただし、無理のない範囲で。前後・左右・回転(内回し・外回し)をそれぞれ30秒~1分間行います。

<棒体操>
肩幅より長めの棒を使います(自宅にあるゴルフクラブや杖、傘、ほうきなど)。 背すじを伸ばしてイスに座って行います。それぞれの運動を10回ずつ行います。
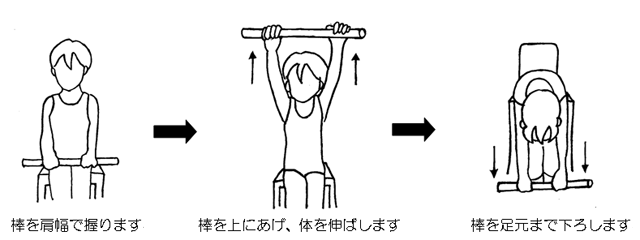
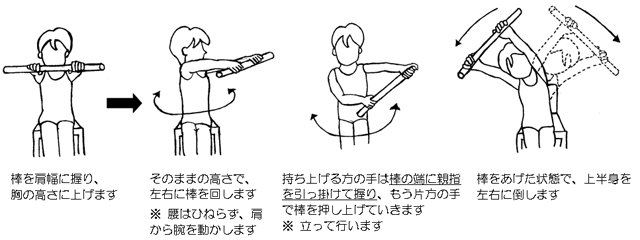
<肩甲骨の体操>
肩の力を抜いて、左右の肩をそれぞれの手で触わり、肘をくるくる回す(前回し・後ろ回し)。 肘の高さと肩の高さが同じくらいになるようにします。 前回しと後ろ回しを交互に10回ずつ、3~5セット行います。
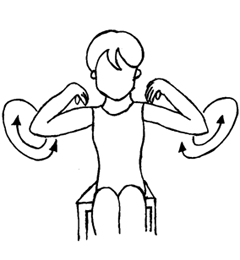
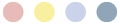
五十肩について
五十肩は中年以降に発生するもので、老化による組織(筋肉、靭帯、関節包など)の変性を基盤として、肩の痛みと運動制限を現す疾患です。 五十肩は長期にわたって痛みが続くことが多く、痛みのために関節を動かさないことで、肩関節の拘縮や肩周辺の筋肉の萎縮を引き起こし、痛みがなくなった後にも残ることがあります。 こうした可動域の制限を残さないために、早期に運動療法を始めることが大切です。
日常生活で注意すること
- 肩を冷やさないよう、保温を心がける(ただし、急性期は冷やします)
- 夜間の痛みがある場合は、寝る姿勢に気をつける
冬にはホッカイロを貼るのも良い(低温ヤケドに注意) 就寝時には布団から肩が出ないような工夫を
痛い肩を上にして横向きに寝る場合は、クッションを抱きかかえる あおむけに寝る場合は、痛い肩の下に丸めたタオルを入れて肩を浮かせる
運動療法
五十肩には、炎症と痛みの強い急性期と、拘縮が現れる慢性期があります。 急性期に無理な運動をすると炎症を悪化させることがありますので、この時期には安静を保つことが大切です。 このため、電気治療や注射によりできるだけ早めに急性期の炎症を抑え、早期に運動療法を始められるようにしましょう。
<アイロン体操>
① 痛くない方の手を台にのせて上半身を前に倒し、痛い方の手でアイロン程度の重さ(約1kg)のおもりを持ちます。
② 肩の力を抜き、からだ全体を揺らすことにより、おもりの重さを利用してゆっくり振ります。
初めは小さく、次第に大きく動かしていきます。ただし、無理のない範囲で。前後・左右・回転(内回し・外回し)をそれぞれ30秒~1分間行います。

<棒体操>
肩幅より長めの棒を使います(自宅にあるゴルフクラブや杖、傘、ほうきなど)。 背すじを伸ばしてイスに座って行います。それぞれの運動を10回ずつ行います。
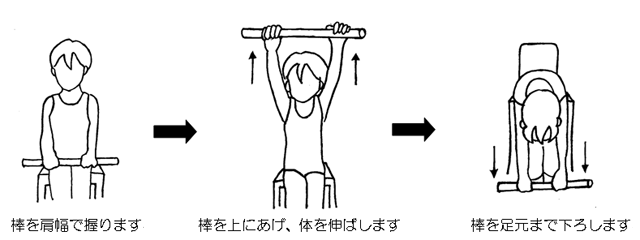
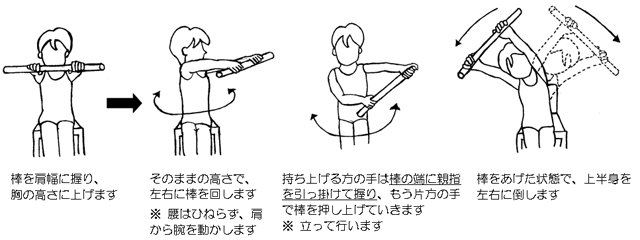
<肩甲骨の体操>
肩の力を抜いて、左右の肩をそれぞれの手で触わり、肘をくるくる回す(前回し・後ろ回し)。 肘の高さと肩の高さが同じくらいになるようにします。 前回しと後ろ回しを交互に10回ずつ、3~5セット行います。
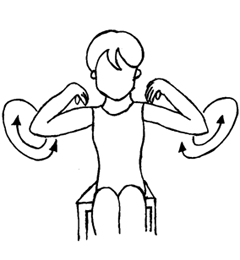
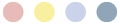
腰痛の自宅療法
背骨の病気の治療では、病院での治療と併せ、日常生活での注意が病状に大きく影響します。 患部に無理をさせる生活をしていたのでは、なかなか治療効果があがりません。 まずは日常生活での姿勢や動作の見直しから始めましょう。次に、症状に応じた運動療法を行います。
腰に負担の少ない姿勢・動作
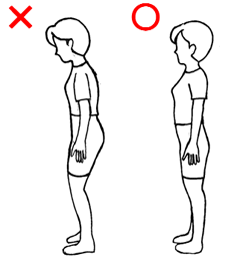
立つときの姿勢
あごを引き、背すじや膝を伸ばします。
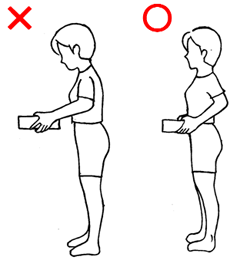
物を持って立つときの姿勢
背すじを伸ばし、物を体に近づけて持ちます。
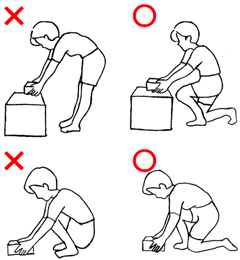
物を持ち上げるときの姿勢
物にできるだけ近づき、片膝をつき、腰を落とします。
背すじを伸ばしたまま立ち上がり、足の力で物を持ち上げます。
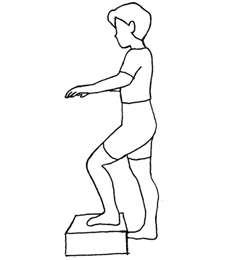
立ち仕事をするときの姿勢
長時間立ち仕事をする場合には、10cm程度の高さの踏み台を用意し、片足ずつ交互に乗せ替えます。
運動療法
① 背骨を支える筋肉の血行を改善し、② 腹筋・背筋の筋力を強化し、③ 椎間関節の動きを良くするなどの目的で行います。
※ストレッチは、筋肉を静かにじわっと伸ばし、その姿勢を20~30秒保持します。
呼吸は自然に。筋肉に軽く張りを感じる程度に心地よく行うこと。
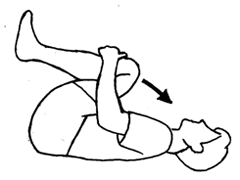
腰背部のストレッチ
仰向けで、両膝を抱えるようにして胸に近づけ、20~30秒保持します。
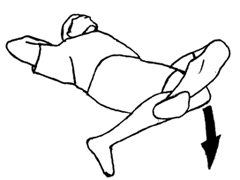
腰部と殿部のストレッチ
仰向けで左脚を右脚の上に組み、左脚で右膝を引っ張って床に近づけていき、右側の殿部を伸ばします。
この時、両肩が床から離れないようにします。
この姿勢を20~30秒保持します。
反対側も同様に行います。
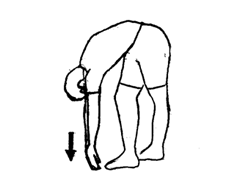
脚の裏側のストレッチ
脚を前後に交差させた状態で、ゆっくり上体を前に倒していき、5~10秒静止してからゆっくり戻します。
左右の脚を組替えて両脚の裏側を伸ばします。
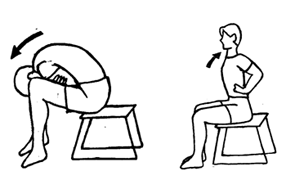
座ってできる簡単なストレッチ
両手で反対側の腕をつかんで左右に背中を広げ、そのまま上体をゆっくり前に倒していきます。
次に、腰に手を当てて胸を張り、ゆっくりと腰を後ろにそらせていきます。
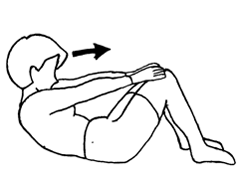
腹筋を鍛える運動
両膝を立てて仰向けに横になります。手が両膝に触れるまでゆっくりと上体を起こし、5~10秒静止してからゆっくり戻します。
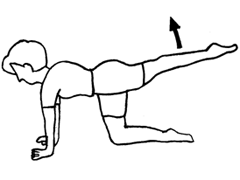
殿部の筋肉を鍛える運動
四つん這いになり、左脚をゆっくりと伸ばしながら上げていき、5~10秒静止してからゆっくり戻します。
反対側も同様に行います。
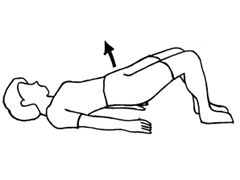
背筋を鍛える運動
両膝を立てて仰向けに横になります。腕は体の脇に伸ばしておきます。そのままお尻をゆっくりと持ち上げ、5~10秒静止してからゆっくり戻します。
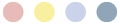
足関節捻挫について
<軽度の損傷>
- 直後~5日目
- 5日目頃~
- 1週間後~
- 3週間後~
足首を固定し、松葉杖による歩行安静、アイシング(直後~翌々日まで)、冷湿布、患部の圧迫(3日程度)、足の挙上
電気治療開始
可動域訓練開始(背屈運動・ふくらはぎのストレッチ)
(※この時期にはまだ底屈は行わないこと)
下腿の前側の筋力トレーニング(足関節の背屈運動、タオルギャザー)
テーピングやサポーターをつけたまま、徐々に体重をかけていく
(かかと歩行、片松葉杖、バランスボードetc)
→ 徐々にウォーキング開始
徐々にスポーツ復帰(電気治療、可動域訓練、筋力トレーニングを継続しながら)
<重度の損傷>
- 直後~2週間
- 2週間後~
- 4週間後~
- 6週間後~
- 8週間後~
足首の固定(ギプス、シーネ)、松葉杖による歩行
電気治療、可動域訓練、筋力トレーニング → 徐々に荷重開始
歩行練習開始、積極的な筋力トレーニング
ランニングなどのスポーツ基本動作開始
徐々にスポーツ復帰(電気治療、可動域訓練、筋力トレーニングを継続しながら)
<慢性捻挫>
電気治療、可動域訓練、筋力トレーニング、基本動作のトレーニング(再発予防)
- アイシング
- ふくらはぎのストレッチ
- 筋力トレーニング
- タオルギャザー
- バランスボード
- カーフレイズ
- ニーベントカーフレイズ
- 基本動作のトレーニング
1回15~20分、40分以上空けて1日6~8回行う。氷嚢で患部を圧迫する。
起立し、丸めたタオル等を足先に入れて傾斜を作る。2~3分×3~5セット。 ストレッチングボードがあればそれを使うのがよい(30°を目標に)。
筋力トレーニングは、20~30回×10セット程度行う
タオルに1~2kgの重りを乗せて行うとよい。
ボードがなければ、片足立ちでバランスを取る練習でもよい。
かかとを床に着けて起立した状態から、つま先立ちになる運動。腓腹筋のトレーニング。
膝を軽く曲げた状態でカーフレイズを行う。ヒラメ筋のトレーニング。
◦ 拇趾球で体重を受け、拇趾球で踏み切ることを意識して歩行する
◦ サイドステップでは、重心を上昇させないまま足離れを良くする
◦ ジャンプからの着地では、膝を軽く曲げた状態で、拇趾球で着地する
◦ ストップ動作では、足先と膝の向きを一致させる(足先が内側に入らないようにする)
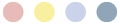
膝の痛みについて
(変形性膝関節症)
膝関節のクッションである軟骨がすり減ったり、太ももの筋力が低下することにより、膝の関節に炎症が起きたり、関節が変形したりして痛みが生じる病気です。 一度発病したら若いころのような膝に戻すことはできませんが、適切な治療を受けることにより症状の進行を遅らせ、普通に日常生活を送ることができます。 また、筋力トレーニングやストレッチなどの自宅療法が非常に有効な疾患です。
治療法と日常生活の注意点
- 変形性膝関節症の治療法
- 日常生活の注意点
- 膝に悪い日常習慣
① 薬物療法(注射、飲み薬、湿布など)、② 電気・温熱療法、③ 運動療法 の3つが基本となります。
① 可動域の維持、② 筋力の維持、③ 運動習慣
正座 とんび座り(ぺちゃんこ座り)~ 正座するときに両方の足が開きW形になる座り方 内股 ~ 膝が内方に向くため、膝のねじれが強くなってしまう →つま先と膝を同じ方向に向けて運動するよう心掛ける
運動療法
- 運動療法の目的
- 運動療法のいろいろ
- 運動療法の行い方
◦︎ |
筋力をつけることで、関節への負担を減らす |
◦ |
関節内の組織の新陳代謝を良くする(関節軟骨が再生するのを助ける) |
◦ |
関節内の組織の新陳代謝を良くする(関節軟骨が再生するのを助ける) |
◦ |
体重をコントロールし、関節への負担を減らす |
ストレッチ、筋力トレーニング、エアロバイク、水中ウォーキングなど
A |
膝外側のこわばりをとる(腸脛靱帯のすべりを改善する) |
B |
ストレッチ ~ 太ももの前面と後面(大腿四頭筋、ハムストリング) |
C |
筋力トレーニング
10~15回×1日2セット行います |
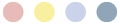
膝の痛み(膝OA)の
自宅療法
以下に紹介するエクササイズは、変形性膝関節症の治療に有効な運動療法です。 靱帯損傷や半月板損傷などの膝関節疾患の場合には症状を悪化させる恐れがありますので、運動療法を始めるときには、必ず医師によく相談してから行うようにしてください。
膝外側の拘縮をとる運動
筋肉を静かにじわっと伸ばし、その姿勢を20~30秒保持します。 呼吸は自然に。筋肉に軽く張りを感じる程度に心地よく行います。 イスに座ったままでできる簡単な体操ですが、可能なら立ち上がって行ってください。
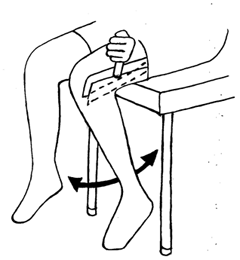
膝を曲げた状態でスジを下に押し込み、足を前後に揺らす
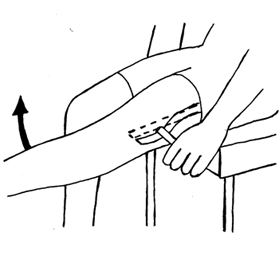
膝を伸ばす際にスジを上に持ち上げる
ストレッチ
筋肉を静かにじわっと伸ばし、その姿勢を20~30秒保持します。 呼吸は自然に。筋肉に軽く張りを感じる程度に心地よく行うこと。
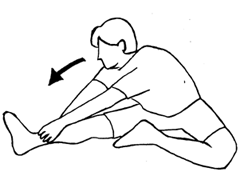
ハムストリングのストレッチ
太ももの後ろ側の筋肉が伸びていることを意識して行います
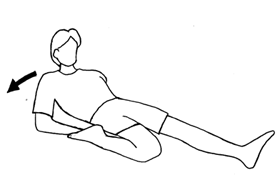
大腿四頭筋のストレッチ
太ももの前側の筋肉が伸びていることを意識して行います
筋力トレーニング
以下のエクササイズからいくつかを選択し、それぞれ10~15回を1日2セット行います。 ただし、膝に水が溜まっている場合は運動を中止し、薬物療法・電気治療を受けてください。
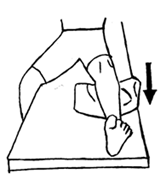
枕つぶし
ふくらはぎの下に枕を置き、つま先をやや外側に向けた状態で、枕をつぶすようにして膝を伸ばす

レッグエクステンション
(イスに座って、仰向けで)
息を吐きながら「1・2・3」で膝を伸ばし、しばらく静止してから「1・2・3」で戻す
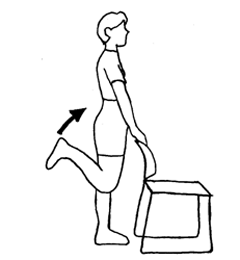
スタンディングレッグカール
息を吐きながら「1・2・3」で膝を曲げ、しばらく静止してから「1・2・3」で戻す
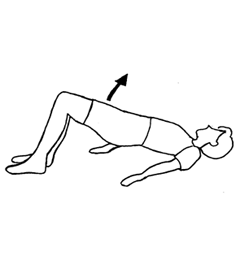
ヒップリフト
息を吐きながら「1・2・3」で腰を浮かし、しばらく静止してから「1・2・3」で戻す

アダクションウィズボール
息を吐きながら「1・2・3」で膝にはさんだボールをつぶし、しばらく静止してから「1・2・3」で戻す
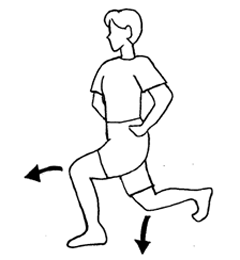
ランジ
「1・2」でしゃがみ込んで静止し、「1・2」で戻す